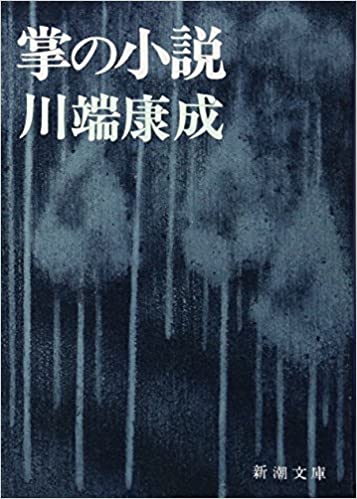川端康成の『駿河の令嬢』を読んでみる
百年前の小説に描かれた御殿場・小山

『伊豆の踊り子』の翌年(1927年/昭和2年)に発表された『駿河の令嬢』は、御殿場と小山での出来事を記した短編小説です。
![]()
川端康成![]()
1899年(明治32年) - 1972年(昭和47年)
日本人初のノーベル文学賞作家
(画像:Wikipedia)
川端康成『駿河 の令嬢』冒頭部分より引用
「ああ、あ、あ、わしらも
汽車が御殿場駅に着いた時でした。その女学生は
この列車は御殿場駅で急に寂しくなります。急行列車でなしに、普通列車で長い旅をした人は知っているでしょう。午前の七時か八時、午後の二時か三時になると列車は花束を一ぱいに積みこみます。これらの汽車通学の女学生の群で、客車の中は何と明るくそして
しかし今の私は長い旅ではありません。
私はその時もうしろから二番目の箱に乗っていました。少女が一時間半と言ったのは沼津駅から駿河駅までのことです。彼女は駿河の少女です。汽車で箱根を越えた人なら知っているでしょう。駿河は山川の向うの大きな紡績工場の窓や庭から女工達が汽車に向って白い布を振る町です。この少女は紡績会社の技師か何かのお嬢さんでしょう。うしろから二つ目の客車へ乗る癖があります。そして一番美しく快活です。
一時間半の汽車、それが
【引用元】『
新潮文庫(昭和四十六年三月十五日初版、平成二十五年四月二十五日七十五刷)収録『駿河の令嬢』
『
むずかしい文章ではないので普通に読めばわかる内容だが、時代背景を知るとさらに理解が深まるので、説明を加えてみよう。
丹那トンネルが開通(1988年/昭和9年)する以前の、御殿場線が東海道線だった時代の話である。ここでの「駿河」とは、御殿場の隣町の小山のこと。御殿場の駅名(停車場名)は当初から御殿場だったが、小山の駅名は小山 → 駿河 → 駿河小山と改められており、小説執筆当時は駿河だった。
川端康成は伊豆に滞在して執筆することが多かったが、月に一度か二度用事で東京へ戻り、その際は三島駅(現在の下土狩駅)から東海道線に乗車し、御殿場や小山を通過していた。三島や沼津の女学校(現在の沼津西高校と三島北高校)へ通う少女たちといつも乗り合わせ、車中で目にしたことを綴った短編が『駿河の令嬢』である。
汽車で女学校に通っていた少女にとっては小山に帰るのに時間がかかり、せめて手前の御殿場であればとの気持ちから「御殿場あたりになりたいよう」という声が出たわけである。
当時は尋常小学校の6年間が義務教育で、その後に2年間の高等小学校まで進めば十分、というのが時代の一般的感覚だった。男子は中学校(旧制中学校)へ、女子は高等女学校へ進むこともあったが、一部の裕福な家庭の子女のみに許された選択肢だった。
小山には富士紡績の工場がありたいへん潤ったが、当時は繊維が日本の対外貿易を支える主要産業であり、現在の自動車産業やIT産業のような先端産業であると同時に日本の稼ぎ頭であった。
紡績会社の幹部社員や技師はエリートであり、東京などの本社から各地の紡績工場に派遣されていたケースも多かった。この少女は、そういった幹部社員や技師の娘だったのだろう。大学に進むことになるのだが、ほんの一握りの恵まれた存在であり、「令嬢」と呼ぶのにふさわしい少女だった。
このあと小説では、東京の大学に進学する「令嬢」と、紡績工場で女工として働いていたが東京へ出ることになった別の少女が駿河駅のホームで言葉を交わすシーンが描かれる。
川端康成の小説には、創作的要素がやや多めに含まれた作品と、実際に体験したことを川端康成の目を通してスケッチのように書き留めた作品がある。『駿河の令嬢』は後者で、与えられた状況が大きく異なる二人の少女の機微の背後に漂う切ない空気感を今でもリアルに感じ取れる作品として読むこともできるし、執筆後百年近くたった令和の現在では、当時の御殿場や小山を知る資料(史料)として読むこともできる。
御殿場や小山は田舎だったが、それでも沼津や三島の女学校に50人程度通っていたらしいこと。東京に進学したり引っ越すことも(多くはなかっただろうが)選択肢としてありえたことがうかがえる。
川端康成自身、作品中で伊豆から東京までを「長い旅ではありません」と書いているが、「いざ行こうと思えば東京に行ける」という自由な雰囲気や風通しのよさのようなものも、鉄道は運んでいたのかもしれない。
富士紡の女工さんは白い布を振ったか?
作品中に気になる記述がある。
「駿河は山川の向うの大きな紡績工場の窓や庭から女工達が汽車に向って白い布を振る町です。」と書かれている。当時の富士紡の女工さんたちは、駿河(小山)駅に停車したり通過したりする汽車の乗客に向かって、白い布を振る習慣があったのだろうか?
川端康成のこの一文からは、「東海道線に乗ったことのある方なら、皆さんご存知でしょう。女工さん達が汽車に向かって白い布を振る"あの町"が駿河(小山)です」といったニュアンスが感じ取れる。周知の事実だったという書き方に感じられる。当時は常識だったと思われることが、今では忘れ去られている。
何かの資料に書き残されているのだろうか? おじいさん、おばあさんから聞いたことのある方はいるだろうか? ご存知の方は教えてください。